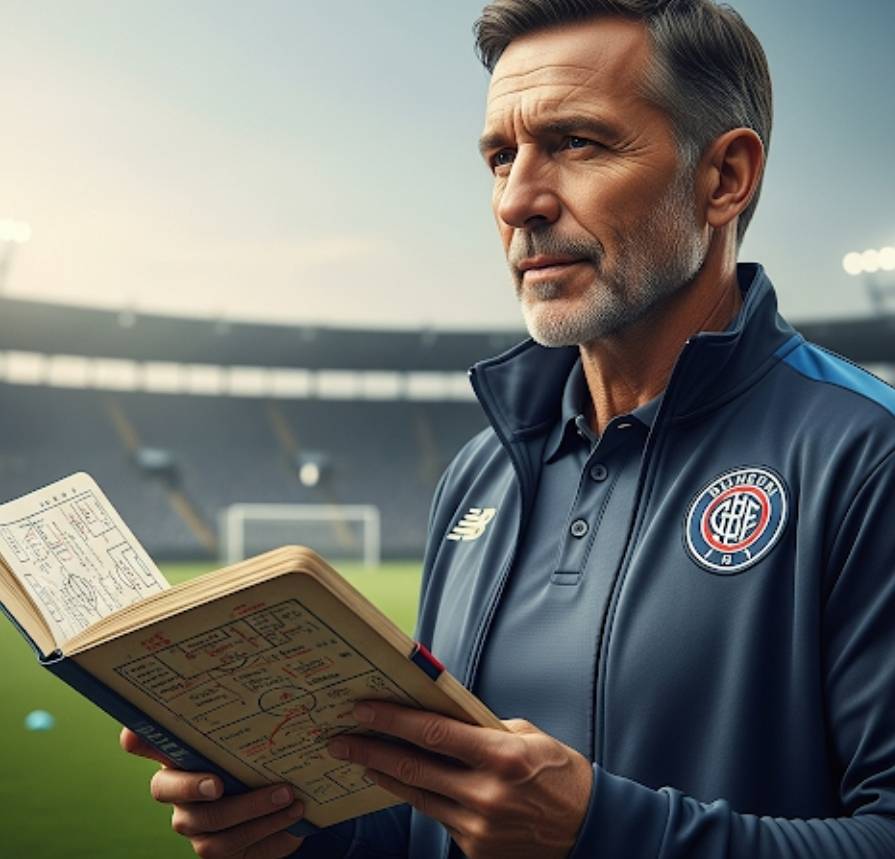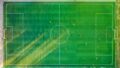サッカーにおける「戦術」とは?
一言で言えば、サッカーの「戦術」とは、チームが試合に勝つために、選手一人ひとりがピッチ上でどのように動き、どのように協力し合うかを定めた共通の「原則」のことです。「設計図」と考えてもいいですね。
もっと具体的に言うと、戦術には大きく分けて2つの側面があります。

1. 攻撃の戦術:点を取るための原則
どうすれば相手ゴールをこじ開けて得点を奪えるのか?そのための筋道を立てるのが攻撃の戦術です。
- どんな形で攻めるのか?:例えば、パスを細かく繋いで相手を崩すのか、それともシンプルに前線に長いボールを蹴って、セカンドボールを拾うのか。
- 誰が、どこで、どんな動きをするのか?:サイドバックがオーバーラップしてクロスを上げるのか、インサイドハーフが飛び出してゴールを狙うのか、それともフォワードがスペースを作って他の選手を活かすのか。
- セットプレーはどうするのか?:コーナーキックやフリーキックの際、誰がどこに走り込み、誰がシュートを狙うのか。
これら全てが、攻撃の戦術に含まれます。
2. 守備の戦術:点を取られないための原則
相手に得点を与えないために、どうすればいいのか?そのための道筋を立てるのが守備の戦術です。
- どこでボールを奪うのか?:相手陣地で前から積極的にプレッシャーをかけるのか、それとも自陣ゴール前でブロックを固めて守るのか。
- 誰が、誰を守るのか?:相手のエースには誰がマークにつくのか、それともゾーンでスペースを埋めて対応するのか。
- 相手の攻撃をどう食い止めるのか?:サイドから崩された時に、どうやって中央を固めるのか、カウンター攻撃に対してどうやって素早く戻るのか。
これら全てが、守備の戦術に含まれます。
なぜ「戦術」が必要なのか?
「別に戦術なんてなくても、みんなが一生懸命走って、うまい選手が点を取ればいいんじゃない?」そう思う人もいるかもしれません。かつての私もずっとそう思っていました。しかし、サッカーは11人で行うスポーツです。もし選手それぞれがバラバラに動いていたら、どうなるでしょうか?
想像してみてください。
パスを出したい選手がパスコースを探しているのに、誰も動いてくれない。 相手に攻め込まれているのに、誰がボールを取りに行くのか、誰がスペースを埋めるのか、誰もわからない。
これでは、まるで混沌とした状態。チームとして機能せず、個々の能力も発揮できません。
戦術があることで、
- チームの動きに「統一感」が生まれる:11人全員が同じ目標に向かって、同じ絵を描きながらプレーできる。
- 個々の選手が「役割」を理解できる:自分が何をすべきか、どこに動くべきか明確になり、迷いなくプレーできる。
- 相手の出方を「予測」し、対応できる:相手の得意な攻撃を封じたり、弱点を突いたりするための準備ができる。
- 試合中に起こる「変化」に対応できる:相手が戦術を変えてきた時に、こちらも修正して対応できる。
つまり、戦術とは、11人の選手が最高のパフォーマンスを発揮し、チームとして機能するための「羅針盤」であり、「共通認識」なんです。

戦術は「魔法」ではない
戦術と聞くと、まるで魔法のように「これをやれば勝てる!」という特別なものだと思う人もいるかもしれません。しかし、そうではありません。
戦術は、あくまで「勝利への道筋」を示すものです。その道筋を辿るためには、選手の技術、体力、そして何よりも「戦術を理解し、実行する能力」が不可欠です。どんなに素晴らしい戦術があっても、それを選手が理解し、ピッチ上で表現できなければ意味がありません。
だからこそ、監督やコーチは、選手に戦術を理解させ、実践させるために、日々トレーニングを重ねるのです。
戦術の種類:無限のバリエーション
サッカーの戦術には、実に様々な種類があります。そして、それは常に進化し続けています。
代表的な戦術の例
- ポゼッションサッカー:ボールを長く保持し、パスを細かく繋いで相手を崩すスタイル。バルセロナやスペイン代表などが得意とする。
- カウンターアタック:守備から一転、素早く攻撃に転じ、少ない人数で相手ゴールを狙うスタイル。守備を固めて、一瞬の隙を突くチームが採用する。イタリアが得意とする守備戦術。
- ゲーゲンプレッシング:ボールを失った瞬間に、すぐに相手にプレッシャーをかけ、高い位置でボールを奪い返すスタイル。ドイツのチームでよく見られる。
- ハイプレス:相手陣地の高い位置から積極的にプレッシャーをかけ、ショートパスを封じ込めるスタイル。
- リトリート:自陣ゴール前で守備を固め、相手にスペースを与えないスタイル。
これらはほんの一部であり、各チームはこれらの戦術を組み合わせて、独自のスタイルを構築します。

フォーメーションと戦術
「4-4-2」や「4-3-3」といったフォーメーションは、選手をピッチ上にどのように配置するかを示すもので、戦術の一部ではありますが、戦術そのものではありません。同じ「4-4-2」のフォーメーションを使っていても、チームによって攻撃の仕方も守備の仕方も全く異なります。
例えば、攻撃的な「4-4-2」もあれば、守備的な「4-4-2」もあります。それは、そのフォーメーションの中で、選手がどのような役割を与えられ、どのように動くのか、という「戦術」によって決まるのです。
戦術は生き物である
戦術は、一度決めたら終わり、というものではありません。まるで生き物のように、常に変化し、進化し続けるものです。
- 対戦相手によって変わる:相手の強みや弱みを分析し、それに合わせて戦術を微調整する。
- 試合展開によって変わる:リードしているのか、追いかける展開なのか、退場者が出たのかなど、試合状況によって戦術を修正する。
- 選手のコンディションや特徴によって変わる:怪我人が出たり、新加入選手がチームにフィットしたりすることで、戦術も柔軟に変化させる。
監督は、試合中に刻一刻と変化する状況を見極め、適切なタイミングで戦術を修正する「采配」を振るう必要があります。これが、サッカーの奥深さであり、監督の腕の見せ所でもあるのです。
私たちが戦術を理解するメリット
サッカーを観るのが好きな私たちも、戦術を少しでも理解することで、その面白さは何倍にも膨れ上がります。
- 試合の見方が変わる:「今、なぜあの選手はあの場所に動いたんだろう?」「このパスは、どういう意図があるんだろう?」と、より深く試合を分析できるようになる。
- 選手のプレーがより面白くなる:個々の選手の技術だけでなく、その選手がチームの戦術の中でどのような役割を果たしているのかがわかることで、プレーの意図が理解でき、より一層楽しめる。
- 監督の采配がより理解できる:なぜあのタイミングで選手交代をしたのか、なぜ戦術を変えたのか、その意図がわかることで、試合をより戦略的に楽しめる。
- サッカーの奥深さを知る:単なるボールを蹴り合うスポーツではなく、綿密な戦略と駆け引きが繰り広げられていることを肌で感じられる。
まとめ:戦術はサッカーの「物語」を紡ぐもの
サッカーにおける「戦術」とは、単なる決まり事ではありません。それは、チームが勝利という目標に向かって、選手一人ひとりがそれぞれの役割を全うし、互いに協力し合いながら、ピッチ上で「物語」を紡いでいくための設計図です。
得点を奪うためのアイデア、ゴールを守るための知恵、そして相手を出し抜くための工夫。これら全てが戦術の中に凝縮されています。
次にサッカーを観る時は、ぜひ「今、チームはどんな戦術で戦っているんだろう?」「あの選手は、この戦術の中でどんな役割を担っているんだろう?」と考えてみてください。きっと、これまでとは全く違う、もっと深く、もっとエキサイティングなサッカーの世界が見えてくるはずです。
サッカーは、単なるボールを蹴り合うスポーツではありません。そこには、選手の情熱があり、監督の哲学があり、そして何よりも、勝利への飽くなき探求心が生み出す「戦術」という名の芸術が存在するのです。